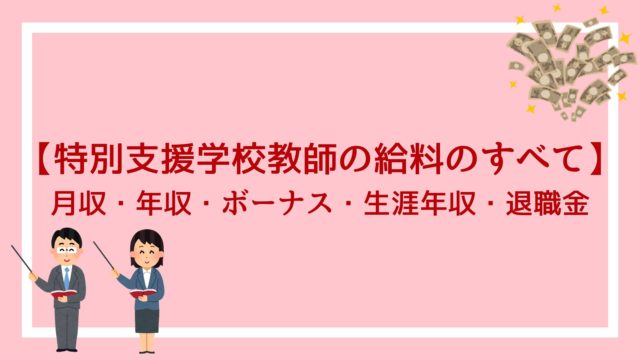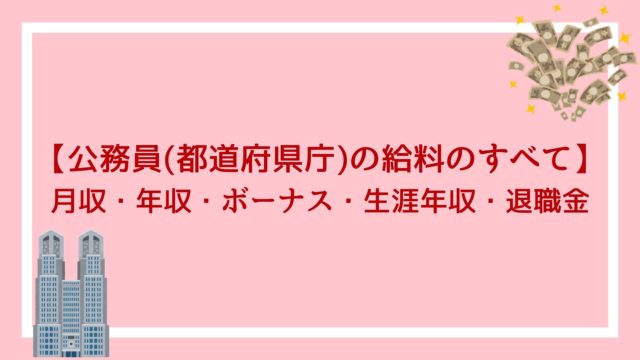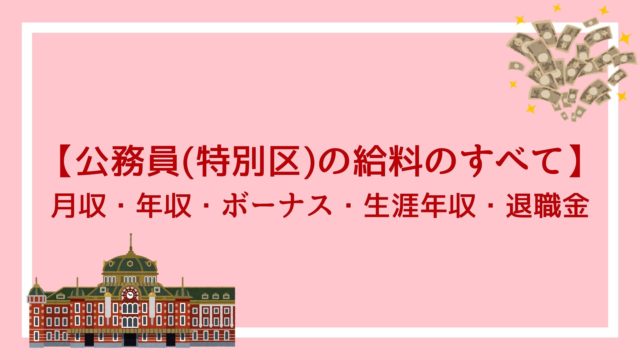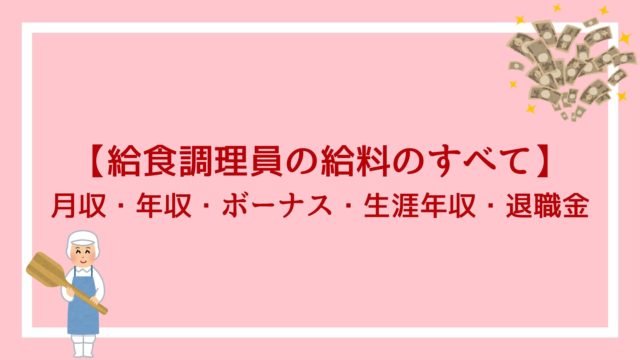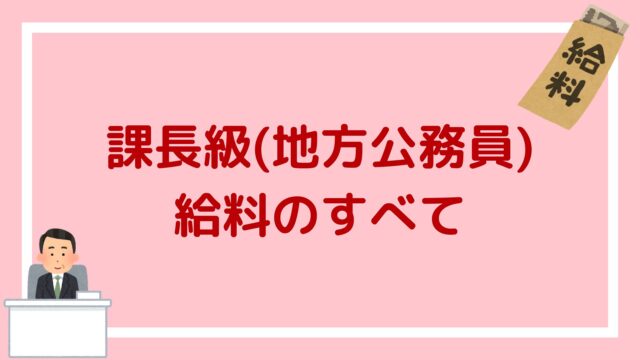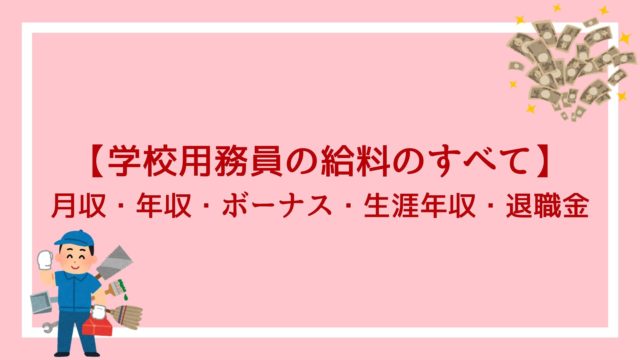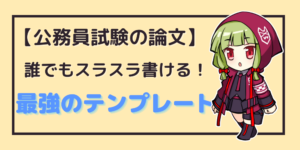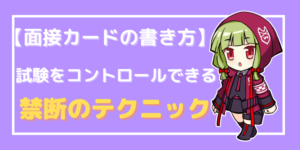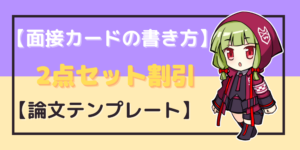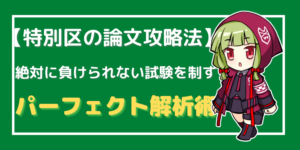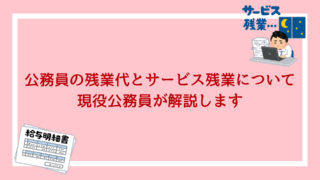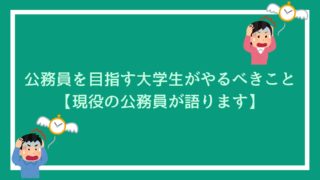もくじ
公務員の給与が上がりにくい理由

公務員の給与制度は、民間企業とは異なる仕組みを持っています。
そのため、昇給や給与の上限に関して特有の課題が存在します。
以下にその主な理由を挙げます。
①:年功序列と俸給表の存在
公務員の給与は、職務の級と号俸によって決定される「俸給表」に基づいています。
この制度では、基本的に年齢や勤続年数に応じて昇給していく年功序列が採用されています。
そのため若いうちは昇給の幅が大きいものの、一定の年齢や号俸に達すると昇給の幅が小さくなり、50歳を迎える頃には年間で2,000円しか上がらない・・・みたいな状況になってしまいます。
②:人事院勧告による給与改定
公務員の給与は民間企業との給与水準の均衡を図るため、人事院が毎年行う「人事院勧告」に基づいて改定されます。
しかし、この勧告は全体的な給与水準の調整を目的としており、個々の職員の昇給には直接的な影響を与えません。
③:昇進の枠が限られている
公務員の昇進はポストの数に限りがあるため、全員が昇進できるわけではありません。
また、昇進には試験や評価が必要であり、競争が激しいため、昇進による給与アップを期待するのは容易ではありません。
公務員の給与制度に対する不満とその背景

多くの公務員が給与の上限や昇給の限界に対して不満を抱いています。
その背景には以下のような要因があります。
①:生活費の増加と給与の停滞
物価の上昇や生活費の増加に対して、給与の伸びが追いつかないと感じる公務員が多くいます。
特に子育てや住宅ローンなどの支出が増える中で、給与の上限に達してしまうと家計のやりくりが難しくなることがあります。
②:民間企業との比較
民間企業では成果に応じた報酬制度やインセンティブが導入されており、努力や成果が給与に反映されやすい傾向があります。
これに対して公務員の給与制度は成果よりも年齢や勤続年数が重視されるため、モチベーションの低下につながることがあります。
③:将来への不安
給与の上限に達すると将来的な収入の増加が見込めなくなります。
そのため老後の生活資金や子どもの教育費など、将来のライフプランに不安を感じる公務員も少なくありません。
公務員の給与制度に対する理解と共感
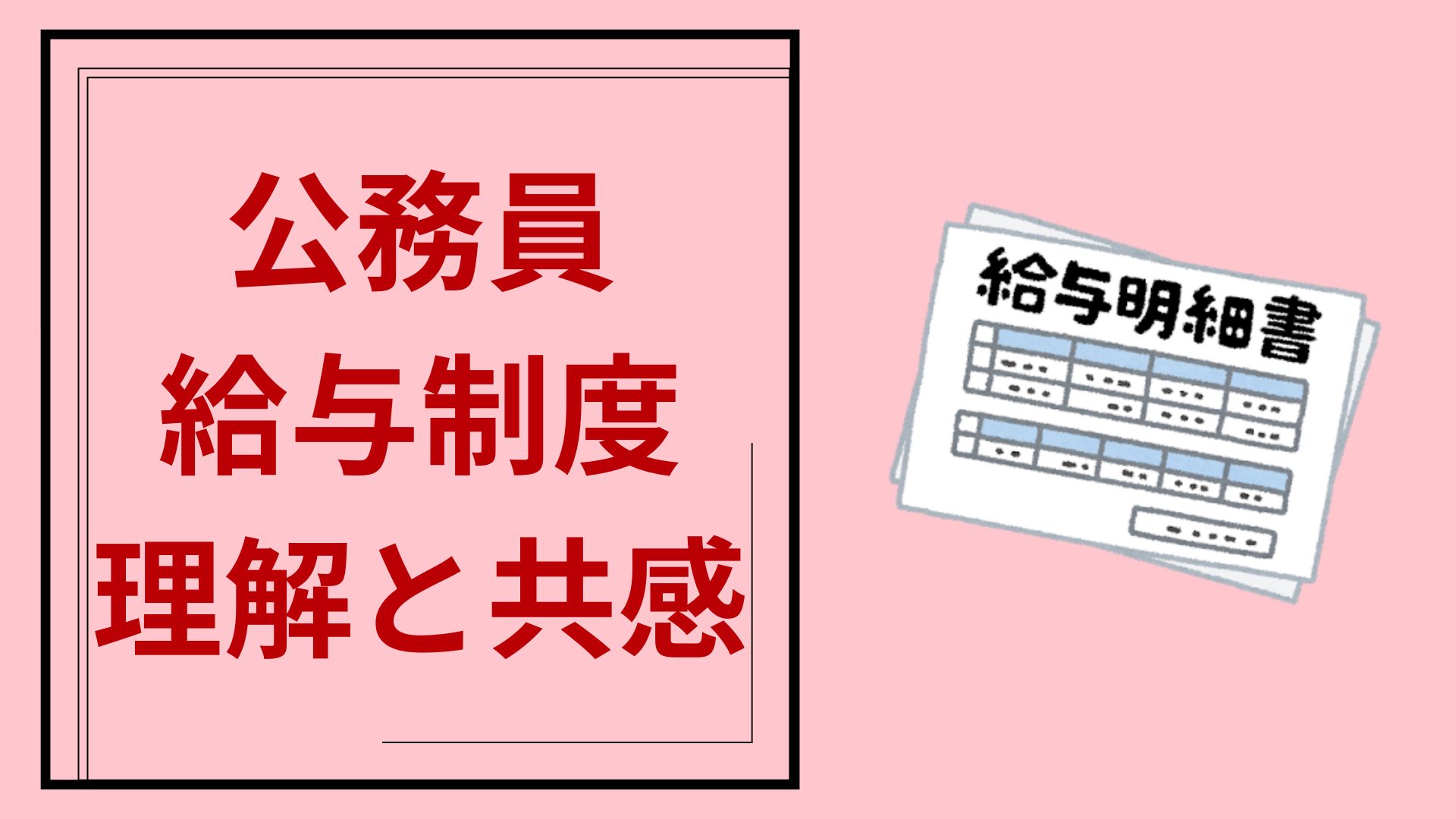
公務員の給与制度には安定性や公平性といった利点がありますが、一方で昇給の限界や給与の上限といった課題も存在します。
これらの課題に対して、以下のような視点から理解と共感を深めることが重要です。
①:安定した雇用と福利厚生
公務員は景気の影響を受けにくく、雇用が安定しているという利点があります。
また各種手当や共済制度など福利厚生も充実しており、長期的な視点で見ると安定した生活基盤を築くことができます。
②:社会貢献とやりがい
公務員の仕事は社会の基盤を支える重要な役割を担っています。
そのため給与だけでなく、社会貢献ややりがいといった非金銭的な報酬も大きな魅力となります。
③:キャリアパスの多様性
公務員の中でも専門職や管理職など、さまざまなキャリアパスが用意されています。
自分の興味や適性に応じて、異動や研修を通じてスキルを磨き、キャリアアップを図ることが可能です。
公務員が収入を増やすための具体的な方法
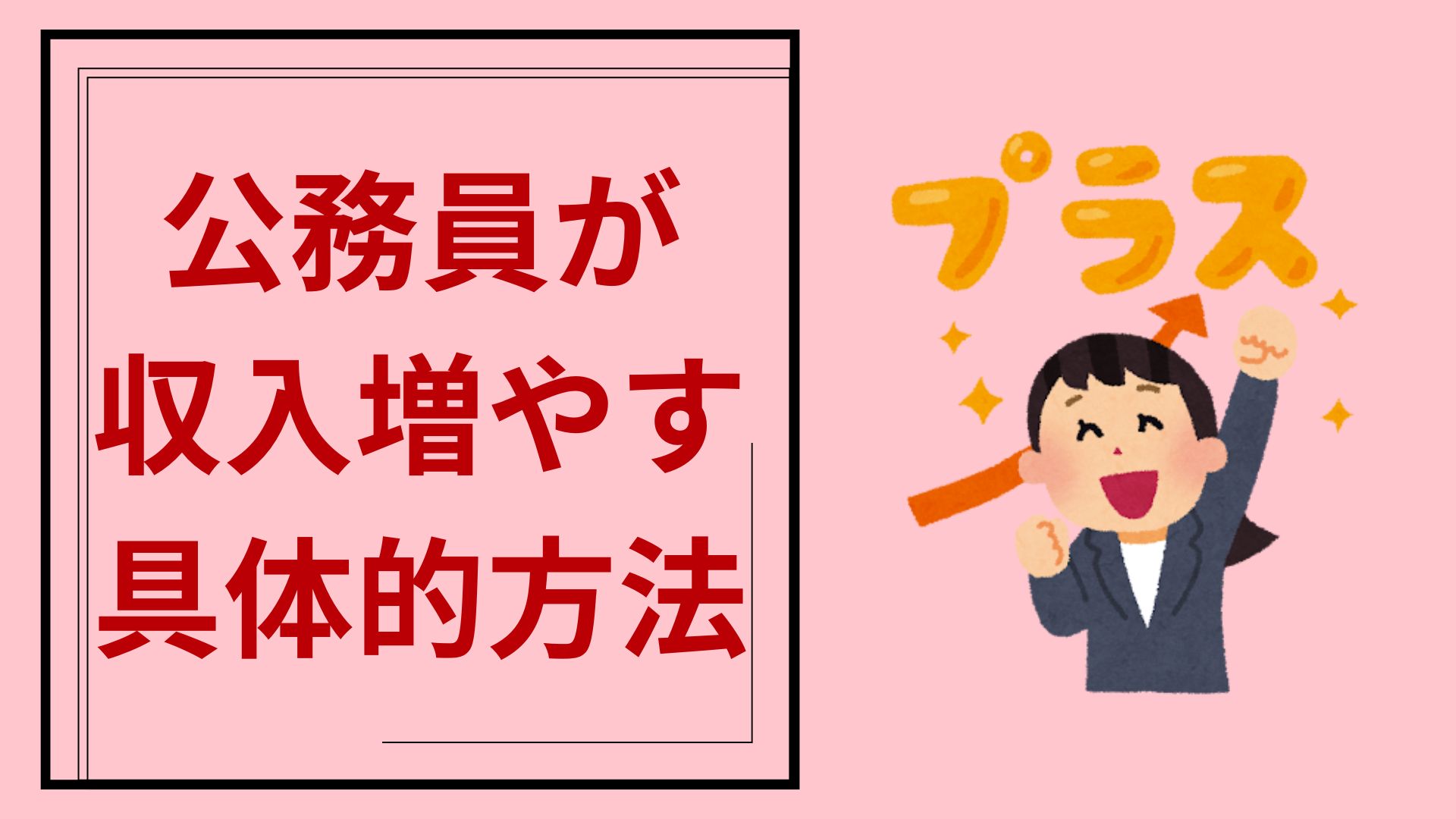
給与の上限や昇給の限界に対して、公務員が収入を増やすためには以下のような方法があります。
①:人事評価の向上を目指す
公務員の昇給は年功序列だけでなく、人事評価にも影響されます。
業務の成果や態度が評価されることで、昇給のスピードが速くなる可能性があります。
そのため日々の業務に真摯に取り組み、上司や同僚との良好な関係を築くことが重要です。
②:資産運用で将来の不安を和らげる
給与の上限がある以上、将来的な収入の伸びを資産形成で補うのは非常に効果的です。
公務員は収入が安定しているため、長期的な視点での資産運用に向いています。
たとえば、
つみたてNISAやiDeCoなどの税制優遇制度を活用する:これらの制度は節税しながら資産形成ができるため、老後資金や教育費の準備に最適です。
インデックス投資による分散投資:市場全体に投資する手法でリスクを抑えつつ、長期的な資産成長が見込めます。
住宅ローンや保険の見直し:支出を最適化することも立派な「収入の確保」です。無駄な保険や、過大な住宅ローンを見直すだけでも、可処分所得は増えます。
投資に不安がある場合は少額から始め、金融リテラシーを少しずつ高めていくことが大切です。
③:スキルアップによってキャリアの選択肢を広げる
たとえ給与に上限があっても、「自分の市場価値を高める」ことで、転職や再任用、セカンドキャリアの可能性が広がります。
・行政職であれば、法務・会計・ITの知識を強化
・技術職であれば、資格取得や研究業績の蓄積
・管理職を目指すのであれば、マネジメント研修や他自治体との交流
また、スキルアップを通じて自治体の課題解決に貢献すれば、人事評価にもプラスに働きます。
④:副業が可能な分野で「知見を活かす」
副業は原則禁止されているものの、以下のような例外的に認められる活動もあります。
講師活動(講演・研修):自分の専門分野を生かしてセミナーを行うことは、職務と関連性が高い場合に許可されやすいです。
執筆活動(専門誌・書籍など):公務に関連する内容であれば、出版も副業ではなく職務の延長線上とみなされることも。
地方創生や地域活動への関与:地域の活性化に資する活動であれば、むしろ推奨されるケースもあります。
こうした活動は、収入に直結することもあれば、セカンドキャリアの布石にもなります。
⑤:生活設計を見直し、「足るを知る」考え方を
「給与が増えない=不幸」ではありません。
むしろ、公務員には他にはない安定という強みがあります。
- 将来の家計をシミュレーションして過度な不安をなくす
- 見栄や周囲との比較で無理な支出をしない
- 家族との時間や健康、趣味など、非金銭的な豊かさに価値を置く
昇給の限界を前提に「無理のない生き方」を考えることが、公務員として長く充実して働くための秘訣です。
まとめ:昇給の限界に悩むあなたへ
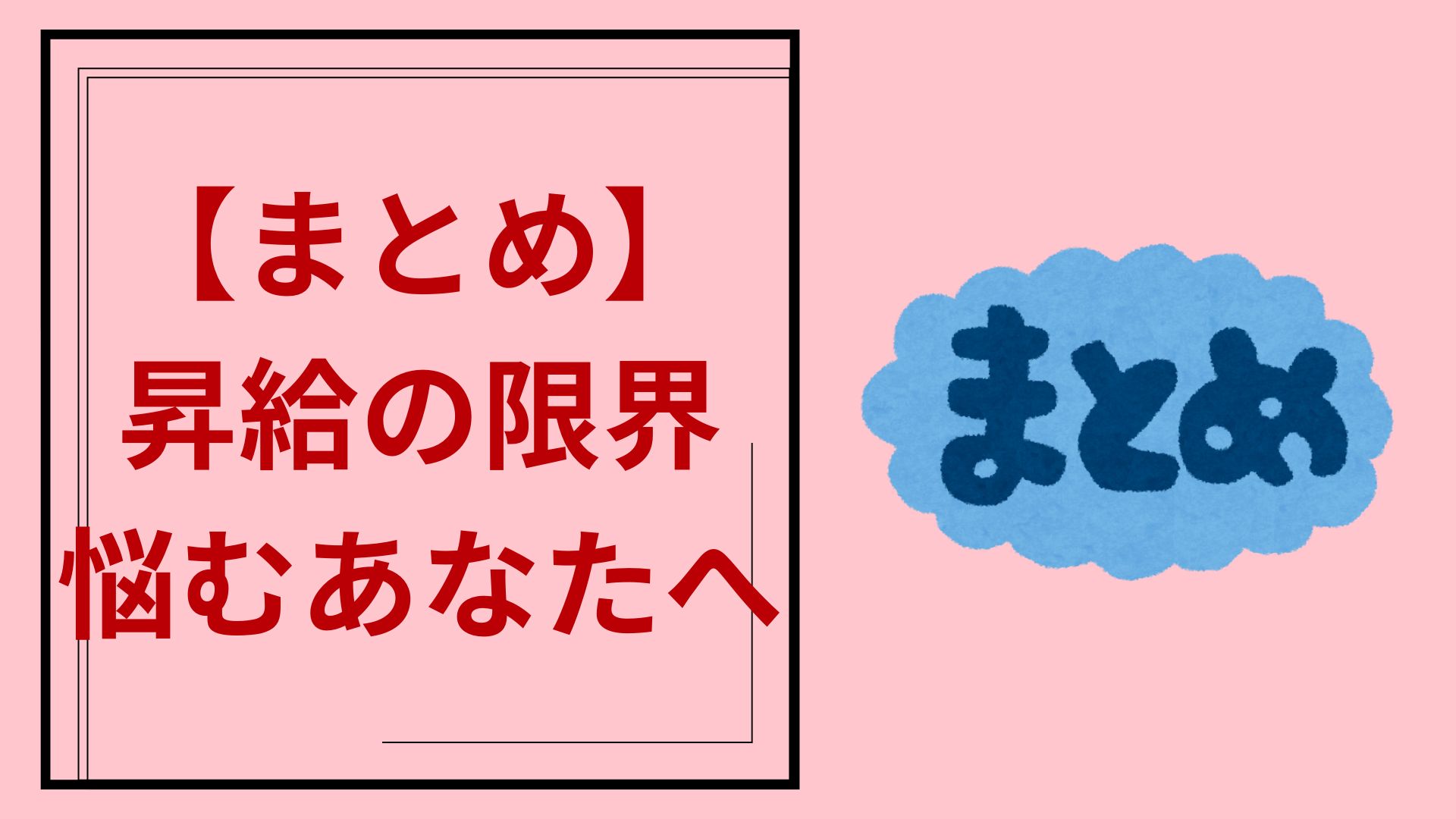
公務員として働く上で、「昇給の限界」という壁にぶつかることは避けられません。
しかし、それは決して人生の限界ではありません。
公務員だからこそ、安定した基盤があるからこそできる、
「堅実な資産形成」
「社会貢献を通じたキャリア形成」
「生活の質を高める知恵と工夫」
こそ、公務員ならではの強みです。
「給与は増えなくても、人生は豊かにできる」
そう実感できるよう、今からできる一歩を踏み出してみてください。
悩みは行動によって、少しずつ光へと変わっていきます。
職場の人間関係で心を疲弊しない秘訣を伝授!
選択次第であなたの人生はどんどん楽になる!
頑張らない・無理しない生き方は確実にトレンド化してる!