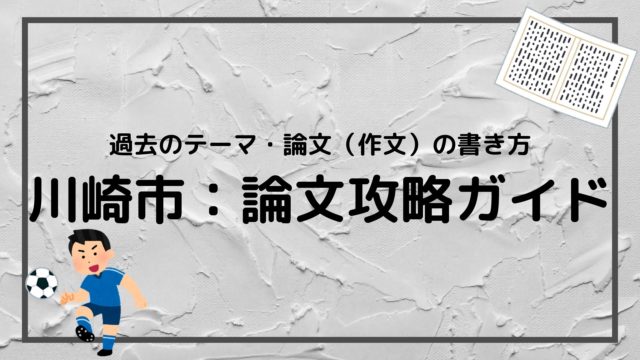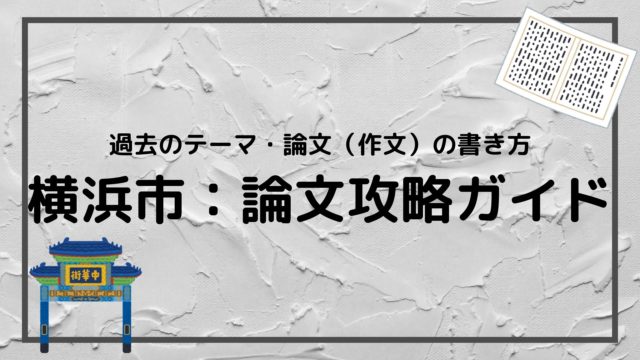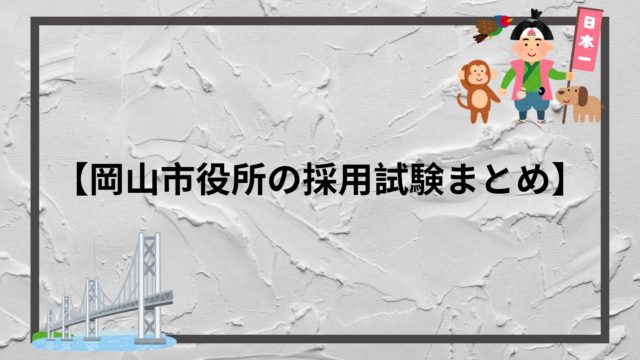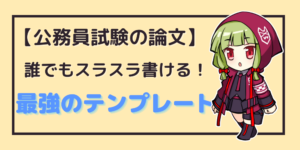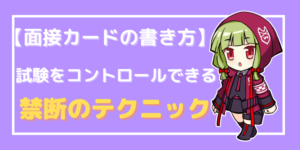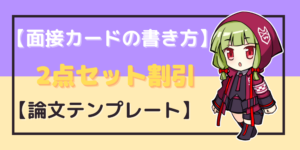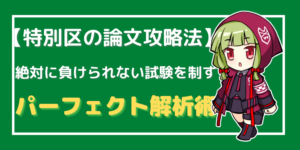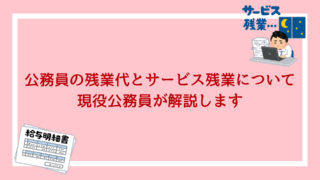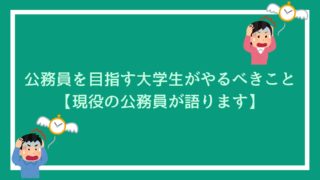・福岡市の論文っていつから対策始めればいいの?
・そもそも論文(作文)の対策ってどうすればいいの?
・過去の出題テーマや書き方のコツがあれば教えてほしい!
このような疑問にお答えする記事になっています!
面接や教養試験の対策はみなさんしっかりと時間をかけて行なっていますが、論文(作文)対策をないがしろにしていないでしょうか?
実は試験に合格する人ほど論文(作文)試験に力を入れているという事実があるのですが、それは論文(作文)試験で差がつきやすいからなんです!
どういったことかと言うと、論文(作文)は自治体側が模範解答(答え)を公表していないため、誰もが手探りで「何となくの対策」をしています。
なので、きちんとした書き方を学んだ人とそうでない人の差が非常に大きく出てしまうんです。
この記事を読むあなたは論文(作文)の書き方とかよく分からない状態で不安だと思いますが、安心してください!
論文(作文)試験は難しいことはなく、書き方のコツ、すなわち「論文(作文)の型」さえ覚えてしまえばむしろ楽勝な試験なんです!
というわけで、
本文では、
- 福岡市:論文(作文)の傾向と対策
- 福岡市:論文(作文)の過去問
- 福岡市:論文(作文)の予想問題
- 福岡市:論文(作文)の書き方
- 福岡市の採用試験に合格する対策法
について解説しています。
ちなみに私はこれまでに受験した採用試験をすべて合格した経験があるのですが、これは自慢話でもなんでもなく、ただ正しい論文(作文)の対策方法を知っていたからなんです!
そんな私が、福岡市の論文(作文)試験で点を稼いで一気に合格に近づけるようになる方法を紹介していきます!
なので、論文(作文)で点を取って福岡市の公務員に絶対になりたい!という熱い思いの方はぜひ記事の最後までお付き合いください。
もくじ
福岡市:論文(作文)の傾向と対策

論文(作文)とは与えられたお題に対して個人の感想ではなく、事実やデータに基づいた内容を論理的に書く試験です。
つまり、あなたがこれまでに書いてきた「◯◯しました。」「◯◯と思いました」といった個人の実体験や感想を書くのではありません。
そのため、社会情勢や自治体が抱える問題等について出来るだけ多くの知識を積み上げておかなければスタートラインに立つことさえ出来ません。
では、令和3年度に福岡市の採用試験で出題された論文(作文)テーマをみてみましょう。
福岡市では、令和2年度から宿泊税※が新たな市の財源となります。これを活用し、福岡市地下鉄空港線全駅において、公衆無線 LANサービスの通信環境の充実を図るなど、観光振興事業を実施していきます。あなたの考える福岡市の観光振興事業等における課題を挙げ、宿泊税などの財源をどのように活用すればよいか、あなたの考えを述べなさい。
※宿泊税…市内のホテルや旅館、民泊などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、条例に基づき使途や税率が定められる法定外目的税。
※福岡市の公式ホームページより引用
まず思うのは「問題文が長い・・・」ということですよね(苦笑)
問題文が短くて内容も簡単な自治体もありますが、福岡市は論文(作文)の難易度が高いとされている特別区(23区)や大阪市、神戸市あたりと互角の難易度と言えますね。
というより、問題文のテイストは特別区の論文(作文)テーマを参考にしている感がありますね。
ちなみに、採用側がなぜ論文(作文)試験を行うか?ですが、
- 受験生がどのような考え方をしているか
- 論理的な考えを文章にするスキルがあるか
この2点をチェックするために行います。
福岡市の論文(作文)は、
① 近年の社会的な問題
② 福岡市の課題や施策について
上記2つを題材にしていることがほとんどです。
このように聞くと「論文(作文)ってすごく難しい・・・」と感じるかもですが、特別区の論文(作文)に似ているからこそ対策しやすいと捉えることも出来ます!
福岡市:論文(作文)の試験時間と文字数
福岡市の論文(作文)の時間と文字数は次の通り。
| 文字数 | 1,000字程度 |
| 時間 | 75分 |
通常、公務員試験の論文(作文)は800〜1,000文字を80分のことが多いため、福岡市も似たような感じですね。
試験時間が75分と聞くと、「いやいや、75分とか長すぎない?」と言う人もいるかもですが、実際に書いてみると800~1,000字の論文(作文)を書くのってけっこうしんどいです。
ただでさえ福岡市の論文(作文)試験は難易度が高いため、テーマを読んで書きたいアイデアが複数浮かび、それを構成通りアウトプット出来るようにしておかないと間違いなく時間は足りませんね。
論文(作文)はだいたいどこの自治体も上限が決められていますが、「◯文字以上書きなさい」という最低限の指定はされていません。
しかし、なるべく上限の1,000字に近い文量の方がいいのは言うまでもありません。
文字数が少なすぎると減点されますので、何はともあれ上限の8割、福岡市では800字は書くように心がけましょう!
論文(作文)試験は一発不合格あるって本当!?
論文(作文)試験では以下の2点をやらかすと「一発不合格」になるかもしれません。
- 極端に文字数が少ない(用紙の半分以下)
- 字が汚くて読みにくい
上記は採用担当者からの評価が最低になりますので注意してください。
文字の綺麗さは個人差あると思いますが、あなたが書ける最高の綺麗さで書きましょう。
福岡市:論文(作文)の配点
| 配点 | |
| 教養 | 100 |
| 専門 | 100 |
| 面接(1次) | 180 |
| 論文(作文) | 40 |
| 面接(2次) | 200 |
※大卒事務職の場合
福岡市の論文(作文)は40点になります。
実施される試験の中で最も配点が低いので、「なんだ、論文(作文)って重要じゃないじゃん!」と思った人はちょっと待ってください!
たしかに福岡市の採用試験では論文(作文)が最も配点が少ないですが、冒頭でもお伝えした通り、論文(作文)は正解が無いので受験生の差が出やすい試験です。
論文(作文)で上手く点を稼げると多少教養試験や面接試験で失敗してもリカバリー出来ますし、教養と面接を人並みにこなしておけば論文(作文)の得点が効いて合格することが出来ます。
つまり、この40点が合否を分ける上で非常に大事なんです!
2次試験に進んだ受験生は当然、面接対策も抜かりありません。
なので、面接試験ってきちんと対策しておけば意外と他の受験生と差がつきにくい試験なんですよね。
ところが論文(作文)はそうはいきません!
苦手意識や不安を抱えたまま試験本番を迎える人が少なくないため、論文(作文)を甘く見ていると不合格に一気に近づいてしまいます。
教養や専門試験って6割くらい取れれば問題ないので過剰に時間を割くのではなく、論文(作文)対策に力を入れた方が合格へは圧倒的に近道になりますね。
福岡市:論文(作文)の過去問

論文(作文)は苦手意識がある人にとっては悩みの種かもですが、実はコツさえ知っていれば誰でもスラスラ簡単に書けるようになります!
ちなみに1つ目のコツですが、
論文(作文)の過去問を利用して対策すること
もっと言えば福岡市の場合、特別区の過去問を利用して対策することですね。
教養試験や専門試験の勉強って、まずは過去問を見て試験のレベルと出題された問題の傾向を把握し、過去問を解きながら進めますよね?
論文(作文)試験の対策も同じで、まずは過去問を知ることから始めます。
上級職等
| 年度 | 過去のテーマ |
| 2024年度 | 令和6年4月に孤独・孤立対策推進法が施行されました。同法では、「孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要である」とされています。 このような立法が行われた背景、また、行政としてどのように取り組んでいけばよいか、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2023年度 | 近年、ChatGPT など、文章や画像を自動的に作成する生成AIは進化を続け、自治体においても、その活用やルールづくりについて検討されています。 生成 AI の可能性とリスクを踏まえ、行政における活用について、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2022年度 | 政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとするカーボンニュートラルを目指すと宣言しました。福岡市も令和2年2月にゼロカーボンシティを表明し、温室効果ガス排出量実質ゼロを目指して、脱炭素社会の実現に向けてチャレンジしています。 脱炭素社会への取組みが求められている背景・課題を述べるとともに、行政としてどのように取り組めばよいか、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2021年度 | 環境省は、2019 年度から 2020 年度にわたり 16 の実証事業(※)を実施し、その優れた取り組み事例を紹介した「熱中症予防ガイダンス」を策定しました。また、これを活用し、地方自治体、施設管理者、企業などが連携して地域の熱中症予防対策を推進することを呼びかけています。 地域の熱中症予防対策の推進について、今後、福岡市はどのように取り組んでいけばよいか、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2020年度 | 福岡市では、令和2年度から宿泊税※が新たな市の財源となります。これを活用し、福岡市地下鉄空港線全駅において、公衆無線 LANサービスの通信環境の充実を図るなど、観光振興事業を実施してい きます。あなたの考える福岡市の観光振興事業等における課題を挙げ、宿泊税などの財源をどのように活用すればよいか、あなたの考えを述べなさい。※宿泊税…市内のホテルや旅館、民泊などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、条例に基づき使途や税率が定められる法定外目的税。 |
| 2019年度 | 福岡市では、「人生100年時代」の到来を見据えて、保健医療という分野から、誰もが健康で自分らしく生き続けられる持続可能な社会システムをつくる100のアクション「福岡100」に取り組んでいます。そこで、あなたの考える「福岡100」のアイデアを1つ挙げ、それを実現するための具体的な取り組みとその効果について述べなさい。
(これまでの取り組み事例) |
| 2018年度 | 福岡市では、IoTやAI等の先端技術に関する民間事業者の提案等を受け入れ、支援するワンストップ窓口「mirai@」(ミライアット)を設置しました。このようなICTの分野に限らず、先進的な民間のノウハウの提案や支援の申し入れがしやすい環境を行政が整備することで、どのような効果が期待されるか、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2017年度 | 商店街は、商品やサービスの提供だけでなく、地域の交流やにぎわいの場としての役割もあるが、近年、郊外大型店の進出や人口減少による市場の縮小などさまざまな要因により、全国的に衰退が進んでいる。商店街のあり方について、あなたが考える課題をあげ、その具体的な対策を述べなさい。 |
| 2016年度 | 福岡市においては、平成28年4月から第3次男女共同参画基本計画をスタートさせ、性別にかかわりなく、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた取組みを進めています。そこで、男女共同参画社会の実現に向けて、どのような課題があり、そのためにどのような解決を図っていくべきか、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2015年度 | 福岡市は、政令指定都市となって今年で43年目を迎えます。現在、政令指定都市は20都市ありますが、福岡市が政令指定都市であることのメリットと、そのメリットを生かし、今後、福岡市はどのように発展していくべきか、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2014年度 | 政府の成長戦略には、女性が安心して仕事にも子育てにも取り組める「女性が輝く日本」が掲げられています。女性が活躍できる社会を実現するための課題と、福岡市ができる取組みについて、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2013年度 | 福岡市の人口は、今年5月1日現在の推計人口が150万人を超え、平成22年国勢調査から平成25年4月1日現在までの人口増加率・増加数がともに政令指定都市で最大となっています。人口の増加により、まちが活気づくなどよい面がありますが、一方では、急激な増加によりさまざまな課題が生じます。そこで人口の増加による功罪と、本市が取り組むべき課題についてあなたの考えを述べなさい。 |
| 2012年度 | 行政機関による情報発信の重要性について、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2011年度 | 身体に障がいのある人が、健やかに、生活しやすい社会とはどのような社会であり、その実現に向けて行政が取り組むべきことについて、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2010年度 | 保育所の待機児童について、なぜこのような問題が起こっているのか、また、待機児童の解消に向けて取り組むべきことについて、行政の立場に立ってあなたの考えを述べなさい |
| 2009年度 | 2005年3月に福岡西方沖地震が起こり、また、近年は集中豪雨(ゲリラ豪雨)などの自然災害が相次いで発生していることを踏まえ、このような災害から市民生活の安全を守り、安心して暮らせるまちづくりのために取り組むべきことについて、行政及び市民の立場から論じなさい。 |
| 2008年度 | 「循環型社会の実現」についてあなたの考えを論じなさい。 |
中級職
| 年度 | 過去のテーマ |
| 2024年度 | 政府は、男女共同参画・女性活躍に関して、指導的地位に占める女性の割合を 2020 年代の可能な限り早期に 30%程度となるよう目指しています。 このような目標が掲げられた背景と、目標を達成するに当たっての課題及び必要な取組みについて、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2023年度 | 福岡市は、様々な事情により義務教育を修了できなかった⼈や、不登校などの事情により義務教育が⼗分に受けられなかった⼈などを対象とする「公立夜間中学校」を設置しました。このような取組みを行っている背景と、市民の就学の機会を確保するために福岡市が今後どのように取り組んでいけばよいかについて、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2022年度 | 福岡市は、高齢者の多様な雇用・就業機会の確保を目指して、福岡労働局と連携し、高齢者の就業を重点的に支援する窓口「シニア・ハローワークふくおか」を開設しました。 このような取組みを行っている背景と、高齢者が活躍できる社会の実現に向けて、福岡市は今後どのように取り組んでいけばよいか、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2021年度 | 近年、子どもの貧困問題が社会的に注目されており、福岡市においても「すべての子どもたちが夢を描けるまち」を目指し、様々な施策を展開しています。 貧困問題を踏まえ、子どもたちが心身ともに健やかに育っていくために、市民や団体などとの連携も含めて福岡市はどのように取り組んでいけばよいか、あなたの考えを述べなさい。 |
初級行政事務および初級学校事務
| 年度 | 過去のテーマ |
| 2024年度 | 福岡市がより「住みやすいまち」となるために必要なことは何ですか。 あなたの考えを述べなさい。 |
| 2023年度 | 災害に備えて、日頃からあなたは何をしておくべきであると考えますか。 |
| 2022年度 | チームで新しい事にチャレンジする時に大切だと考えること |
| 2021年度 | 福岡市役所に入庁したあなたの10年後の姿について |
社会人経験者
| 年度 | 過去のテーマ |
| 2023年度 | ※2023年より論文試験は廃止 |
| 2022年度 | 福岡市では、政治意識を高めるための啓発事業として、「明るい選挙啓発事業(ポスターコンクール、出前授業等)」を実施しています。令和4年度から令和5年度にかけては、福岡市長及び福岡市議会議員の任期満了に伴う選挙が執行されますが、多くの人が参加し、公正かつ適正な選挙を実現するために、福岡市はどのように取り組んでいけばよいか、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2021年度 | 福岡市では、自治協議会と市がパートナーとして、様々な主体と地域の未来を共に創る「共創」の取り組みを推進するとともに、持続可能な地域コミュニティの実現に向けて、自治協議会や自治会・町内会の位置づけや地域への支援のあり方などについて検討を進めています。 あなたが考える「持続可能な地域コミュニティ」とはどのようなものですか。また、その実現のために、福岡市はどのように取り組んでいけばよいか、あなたの考えを述べなさい。 |
就職氷河期世代を対象
| 年度 | 過去のテーマ |
| 2024年度 | 福岡市では、人生100年時代の到来を見据え、誰もが心身ともに健康で自分らしく活躍できる持続可能なまちを目指すプロジェクト「福岡100」の取組みの一つとして、認知症の人やその家族がいきいきと暮らせる認知症にやさしいまち、「認知症フレンドリーシティ」を目指しています。 「認知症の人にやさしいまち」とは、どのようなまちだと思いますか。また、それを実現するためにどのような取組みが必要か、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2023年度 | 政府は、次元の異なる少子化対策の実現に向けて令和5年6月 13日に「こども未来戦略方針」を閣議決定しました。 福岡市においても、令和5年度から第2子以降の保育料を無償化するなど、子どもを望む人が、安心して出産、子育てができるよう子育て支援の充実に取り組んでいます。 今後、少子化が地方自治に与える影響を踏まえ、安心して出産、子育てができる社会の実現に向けて、福岡市はどのように取り組んでいけばよいか、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2022年度 | 福岡市では、政治意識を高めるための啓発事業として、「明るい選挙啓発事業(ポスターコンクール、出前授業等)」を実施しています。令和4年度から令和5年度にかけては、福岡市長及び福岡市議会議員の任期満了に伴う選挙が執行されますが、多くの人が参加し、公正かつ適正な選挙を実現するために、福岡市はどのように取り組んでいけばよいか、あなたの考えを述べなさい。 |
| 2021年度 | 福岡市では、自治協議会と市がパートナーとして、様々な主体と地域の未来を共に創る「共創」の取り組みを推進するとともに、持続可能な地域コミュニティの実現に向けて、自治協議会や自治会・町内会の位置づけや地域への支援のあり方などについて検討を進めています。 あなたが考える「持続可能な地域コミュニティ」とはどのようなものですか。また、その実現のために、福岡市はどのように取り組んでいけばよいか、あなたの考えを述べなさい。 |
障がい者を対象
| 年度 | 過去のテーマ |
| 2024年度 | あなたが市職員となった場合、市民から信頼される公務員となるために必要なことは何ですか。 あなたの考えを述べなさい。 |
| 2023年度 | 市民や職場の仲間たちと信頼関係を築くために大切だと考えること |
| 2022年度 | 「自分らしさ」を発揮できた経験について |
| 2021年度 | 社会人として心がけていきたいこと |
※福岡市の公式ホームページより引用
基本的に社会問題や自身のこれまでの経験を絡めた内容がお題として出題されています。
この過去のテーマが論文(作文)対策をする上で最も重要なのですが、その理由はシンプルに、
論文(作文)は過去問と似たようなテーマが出題されるから
論文(作文)のテーマは無数にある訳ではありません。
- 少子高齢化
- 環境問題
- 住みやすいまちづくりをするために
このような公務員試験で頻出のテーマが取り入れられ、テーマの切り口を少し変えて出題されています。
だからこそ過去問を知るか知らないかで論文(作文)の書きやすさは大きく変わってくる訳ですね。
福岡市:論文(作文)の予想問題
次に、過去問だけでなく「福岡市の採用試験でこれから出題が予想される論文テーマ」を特別にここだけで教えます。
| 予想テーマ | |
| 1 | 福岡市における都市の成長と持続可能性の両立
アジアの玄関口として発展を続ける福岡市において、都市の成長と環境・暮らしの持続可能性を両立させるために公務員として何ができるか述べなさい。 |
| 2 | 若者の定住と雇用の確保に向けて
若者が働き、暮らし続けたいと感じるまちをつくるために、福岡市が行うべき支援策について述べなさい。 |
| 3 | 子育てしやすいまちづくり
出生率が高い福岡市において、今後さらに子育て支援を充実させるために必要な取り組みについて述べなさい。 |
| 4 | 観光都市としての魅力強化と地域経済活性化
観光客や国際会議の誘致が進む福岡市において、地域経済の活性化につなげるための方策について述べなさい。 |
| 5 | 災害に強いまちづくり
大雨や地震などの自然災害に備えるために、福岡市としてどのような対策が必要か、公務員の視点から述べなさい。 |
| 6 | デジタル技術を活用した行政サービスの向上
スマートシティを目指す福岡市において、デジタル技術を活用して市民の利便性を高めるための取り組みについて述べなさい。 |
| 7 | 高齢社会における地域福祉の充実
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、福岡市が取り組むべき福祉政策について述べなさい。 |
| 8 | 多文化共生の推進に向けた行政の役割
外国人居住者が増加する中で、福岡市が目指す多文化共生社会の実現に向けた具体的な取り組みについて述べなさい。 |
| 9 | 市民との協働による地域課題の解決
地域の課題を行政だけでなく市民とともに解決していくために必要な姿勢や方法について述べなさい。 |
| 10 | 公務員として求められる姿勢と責任
住民の信頼を得て市民に寄り添う行政を実現するために、公務員として大切にすべき心構えについて述べなさい。 |
福岡市:論文(作文)の書き方

論文(作文)の対策方法は以下の5ステップになります。
- テーマの理解と分析
- 論理的な構成
- 文体と表現力
- 使い回せるフレーズを自分のモノにする
- 模範解答の活用
①:テーマの理解と分析
与えられたテーマや問題文をよく読み、理解することが重要です。
テーマの核心をつかみ、分析する能力が求められます。
また、テーマを多角的に考え、関連する情報や視点を収集しましょう。
②:論理的な構成
論文は明確な構成を持つ必要があります。
一般的な構成は、序論、本論(論点や論証の展開)、結論の3つのパートからなります。
序論ではテーマの背景や重要性を説明し、本論では主張や論証を展開し、結論ではまとめや提言を行います。
③:文体と表現力
文体は公務員として求められる明瞭かつ公正な表現を意識しましょう。
冗長な表現や曖昧な表現を避け、簡潔かつ具体的な言葉を使うようにすると評価ポイントが高くなります。
また、適切な引用や参考文献を使用できるよう、知識として頭に入れておくといいですね。
④:使い回せるフレーズを自分のモノにする
論文(作文)の模範解答を読み込むと、使い回せるフレーズというのが自然と分かってきます。
というのも、一見テーマが異なるようでも、取り上げられる課題に対する施策で同じものが使えることがよくあるからです。
といったように、模範解答をしっかりと読み込むことで、「この言い回しは何度も出てきたな」といったことに気がつくようになります。
これをそっくりそのまま覚えておけば、使い回せるテーマが出てきたときにオートマチックにスラスラと書くことが出来るので超オススメです!
⑤:模範解答の活用
「論文(作文)はコツさえ知れば誰でもスラスラ書けるようになる」と言っていますが、その最大のコツとは「論文(作文)の模範解答を知ること」です。
模範解答はある意味、テンプレートや雛形に近いもので、テーマで問われる内容、施策に対するフレーズをすべて自分の引き出しとしてプールしておくことが論文(作文)の最大のコツになります。
この「フレーズ」は論文(作文)を書く上で超重要でして、自分でその場で思いついて書いたものはチグハグな文章になったり話が飛んだり、最悪何が言いたいのかよく分からない文章が出来上がってしまいます。
逆に「フレーズ」を知っていれば、文体の一致や文章の構成が自然と身につき、どんなテーマでも悩むことなく、面白いように言葉が降ってきて書けるようになります!
また、過去のテーマで書いてみた文章は似たテーマの時に使い回すことが出来るため、模範解答と同レベルの論文(作文)が簡単に書けるようになります。
ちなみに論文(作文)の頻出のテーマ + 模範解答を知る方法は、
私が執筆したノウハウnoteを読み込むこと
この方法で自然と身につけることが出来ます。
模範解答(正しく書かれた論文)というのは、構成・文体がきちんとしていますからね。
ちなみにノウハウnoteについては記事の最後で紹介していますので、このまま読み進めてください!
福岡市・論文攻略ガイドまとめ

この記事を読んでいるあなたは、
どんなテーマでもスラスラ論文(作文)が書けるようになりたい!
このように考えているのではないでしょうか?
現在、インターネット上では、
大量の論文(作文)ノウハウがあふれかえっています。
公務員アドバイザーを名乗る人の発信するLINEに登録してみたり、
書店で参考書を購入したりして、「論文(作文)を書く方法」について勉強している方も多くいらっしゃると思います。
しかし!
現在のインターネット上、もしくは参考書で解説されている論文(作文)ノウハウには、1つの大きな問題があることにあなたは気づいているでしょうか?
再現性のないテクニックでは上達しない
現在、あなたが
「これなら書けそうだ!」
と感じている(勉強している)ノウハウは、以下のような内容ではないでしょうか?
- 過去問を調べろ!
- 過去問を用いて自分で実際に書いてみろ!
- 書いた論文を添削してもらえ!
このように、いわゆる
「過去問を解いて経験値を増やせ!」
というノウハウです。
過去問を研究するという勉強法は確かに有効です。
実際私が進めるテクニックも過去問を用いて実際に自分で書いてみようという内容なので、基本路線は同じ。
しかし、実際に自分で論文(作文)を書いてみたところで、
- 書き方を知らない
- 論文(作文)の構成を知らない
このような人が行っても、実行するのに膨大な時間がかかってしまいます。
論文(作文)1つにつき90分、10テーマ書くと900分。15時間以上・・・。
公務員を目指すあなたは論文(作文)をまず書いてみるだけで15時間も時間をかけれるほど暇ではありませんよね?
また、書いた論文を添削してもらえ!と言われても、公務員予備校に通ってるとかじゃないと「誰に添削してもらえばいいの?」ですよね。
つまり、
多くの公務員アドバイザーが提唱しているノウハウは、
再現性が非常に低い
とは思いませんか?
ノウハウを実行すると合格できるというより、ノウハウを実行すること自体が難易度が高すぎるのです。
再現性のないノウハウで、お金と貴重な時間を時間を浪費するのはそろそろやめにしませんか?
あなただけに教える!論文(作文)をマスターする方法
私自身は、公務員予備校に通って努力し、受験したすべての公務員試験に合格してきました。
これは特別私が優秀だったからでも何でもなく、ただ単に「正しい努力」を「正しい量だけ行った」からなんです。
もちろん、公務員予備校で教わった知識・ノウハウ・テクニックをもとに猛勉強をしました。
ただ、それと引き換えに貴重な時間とお金をたくさん犠牲にしてきました。
この記事を読むあなたにはそんな私が行ったよりももっと効率が良い方法で対策してほしい、ましてや巷(ちまた)にあふれる再現性の低いノウハウに振り回されてほしくないんです。
そんな訳で、大学卒業程度の試験区分の採用試験を受ける方のために、頻出・出題が予想されるテーマを合計35個厳選し、さらに35テーマ分、すべてで模範論文を作成しました。
また、高卒区分の試験を受ける方のためには、作文テーマで頻出のものから30テーマ分を厳選し、こちらも試験でそのまま使える模範作文を作成しました。
そこらへんに転がっている小手先のテクニックよりも、もっと効率が良く、汎用性の高いフレーズがギッシリ詰まっています。
また、すべて1つの流れで書いているので、この模範解答で型を覚えれば、どんなテーマが出題されようとスラスラ書けるようになります。
福岡市の採用試験に合格したいと考えているなら、この模範解答は真っ先に見るべきです。
ノウハウnoteを見ながら、しっかりと勉強すれば、あなたは確実に変われます。
一生条件の悪い仕事のまま、朝から晩まで働かなくて良いんです。
公務員になれば定年まで安定した生活ができ、あなたの小さい頃からの憧れ、夢を実現させることが出来ます。
少し興味が湧いてきましたか?
何度も言いますが、私が執筆した模範論文、模範作文を読めば文章スキルを劇的に向上させることができます。
本気で
「論文(作文)の書き方を学びたい!」
「公務員に絶対になるんだ!」
「安定した人生を生きる!」
という強い意志のある方は、ぜひ下記のnoteを手にとって活用してみてください。
私の論文(作文)ノウハウnoteは、「大卒区分」「高卒区分」「社会人経験者区分」と、それぞれ受験する試験に合わせたものを用意しております。
公務員になるというあなたの夢を実現するためにも、今この機会にぜひ私のnoteを手に取って試験対策をしてみませんか?

↓↓ 面白いくらいスラスラ書ける! ↓↓
大卒区分で論文試験がある方向け
高卒区分で作文試験がある方向け
社会人経験者区分で論文(作文)がある方向け

攻略ガイド】過去の出題文テーマと最強の対策方法を紹介-1280x720.jpg)