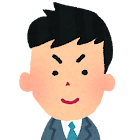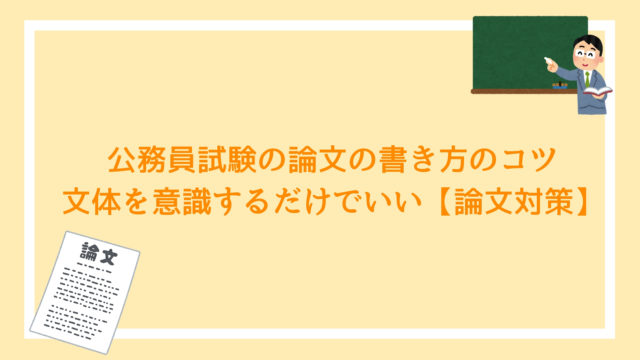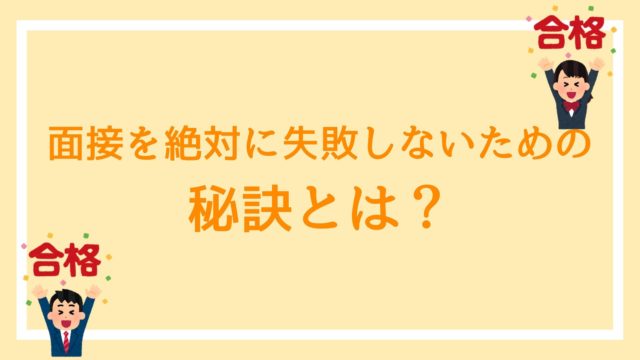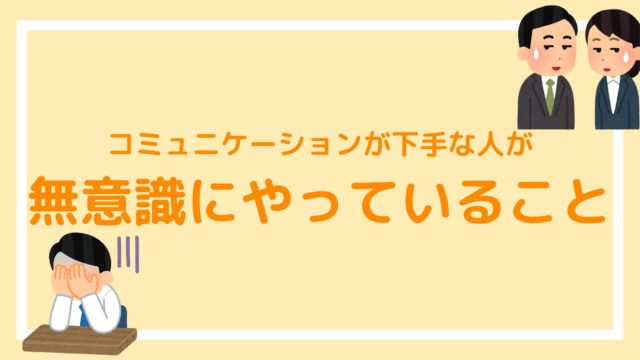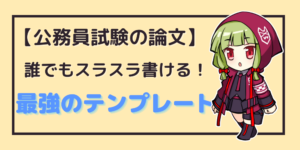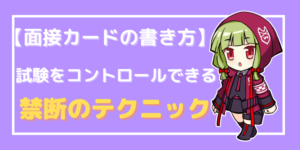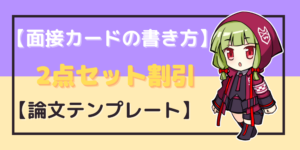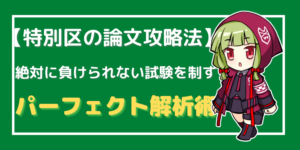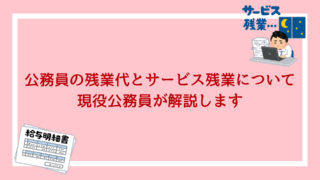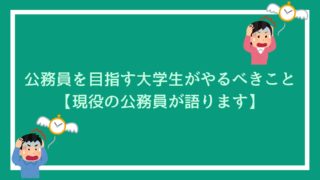社会人経験者枠の公務員試験では、これまでの職務経験の中で、
「どんな人間関係を築いてきたか」
「どんな組織運営に携わってきたか」
が重視されます。
中でもとくに多い質問のひとつが、
一見シンプルですが、この質問には組織マネジメント力・指導の考え方・人材育成への意識が問われており、ただ「教えました」「フォローしました」と答えるだけでは面接官の心に響きません。
というわけで、
本文では、
好印象を与えられる答え方の考え方と具体例
を解説していきます。
社会人枠の採用試験はどの自治体も倍率が高く、狭き門であることで知られていますが、この記事を読んで答え方の知識を身に付けることで合格に一歩近づけるはず。
なので、社会人枠の試験を受験される方はぜひ記事の最後までお付き合いくださいね。
なぜ「ただやり方を教える」では不十分なのか
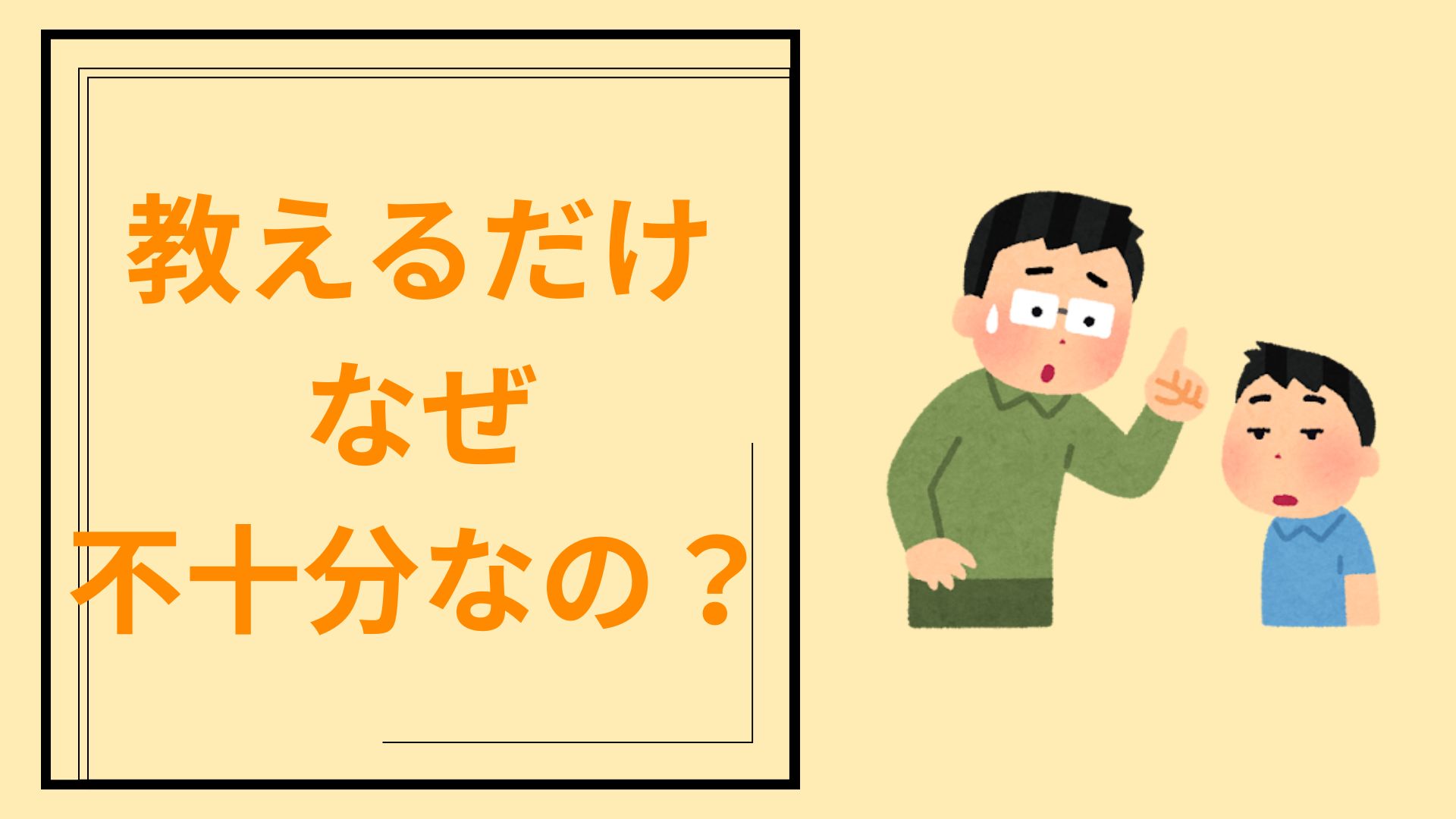
この手の質問で、よくある回答が以下の2パターンです。
一見すると誠実そうに見えますが、これだけでは表面的な指導者とみなされ、面接官には響きません。理由は以下の通りです。
⚠やり方を教えるだけでは相手の理解度や苦手ポイントを把握できず、成長につながらない
⚠質問しやすい環境を作っても、質問する側が「何が分からないのか」すら整理できないケースも多い
⚠「指導=教えること」だけだと、自治体の現場で必要な“主体性を育てる指導力”が不足していると判断される
特に公務員の現場はマニュアルがない場面も多く、その都度自分で考えて判断する力が求められます。
そのため、単に「教える・聞きやすい環境を作る」では指導の本質には届かないのです。
指導の本質は「自分の頭で考え、成長できる環境をつくること」
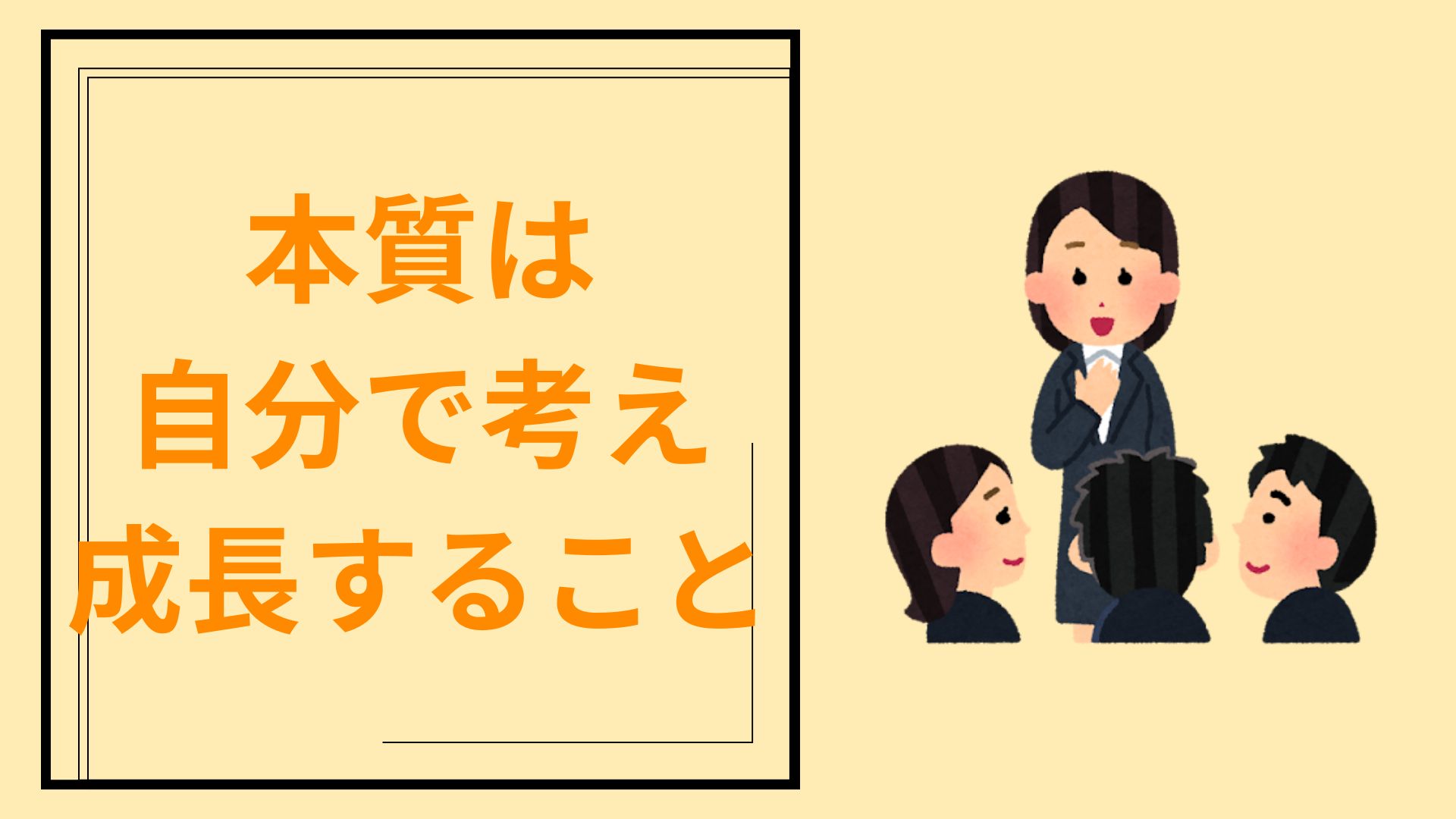
社会人経験者枠の受験者には、一般枠と違い「現場で部下・後輩を育成した経験」が期待されています。
自治体の面接官もその点を重視しており、ただの作業指導だけでなく、相手が自分で考え行動できる人材になるよう導く力を問いたいのです。
そこで理想の答え方はこうです。
「私は後輩の成長を考え、ただやり方を伝えるのではなく、まず本人に考えさせ、どこでつまずいているのか、何が難しいのかを一緒に整理することを意識しています。その上で、どう考えればうまくいくかを本人と考え、再発防止につながるよう指導してきました」
このように、「教える」ではなく、「考える場を作る」というスタンスを示すと、指導の本質を理解していると評価されやすくなります。
さらに面接官の心に響くのは「具体的なエピソード」
たとえば、
「以前、後輩社員が顧客対応の手続きでミスをした際、その場で手順を教えるだけでなく、何が分かりにくかったのかを一緒に振り返りました。すると、書類の説明項目があいまいだったことに気づき、改善策を提案してもらった経験があります」
このように指導を通じて相手の成長を促したエピソードを添えると説得力が増します。
「つまづいた点を一緒に考える」スタンスで関係性を構築する

指導時に大切なのは、相手の状況や性格を踏まえた上で「どこでつまづいたのか」を一緒に考える姿勢です。
これによって後輩は「ただ怒られた」「ただやり方を押し付けられた」と感じず、主体的に学ぼうとする意欲が生まれます。
具体的には以下の流れを意識すると効果的です。
📌まず本人の考えを聞く
📌理由を一緒に整理する
📌考え方の癖や苦手分野を把握する
📌解決方法を一緒に考える
📌再発防止策をまとめる
このプロセスを繰り返せば、後輩はミスの原因を自分で整理できるようになり、応用力も高まります。
公務員の現場で求められる「臨機応変な対応力」を養う上でも非常に重要なアプローチです。
まとめ:後輩指導の答え方
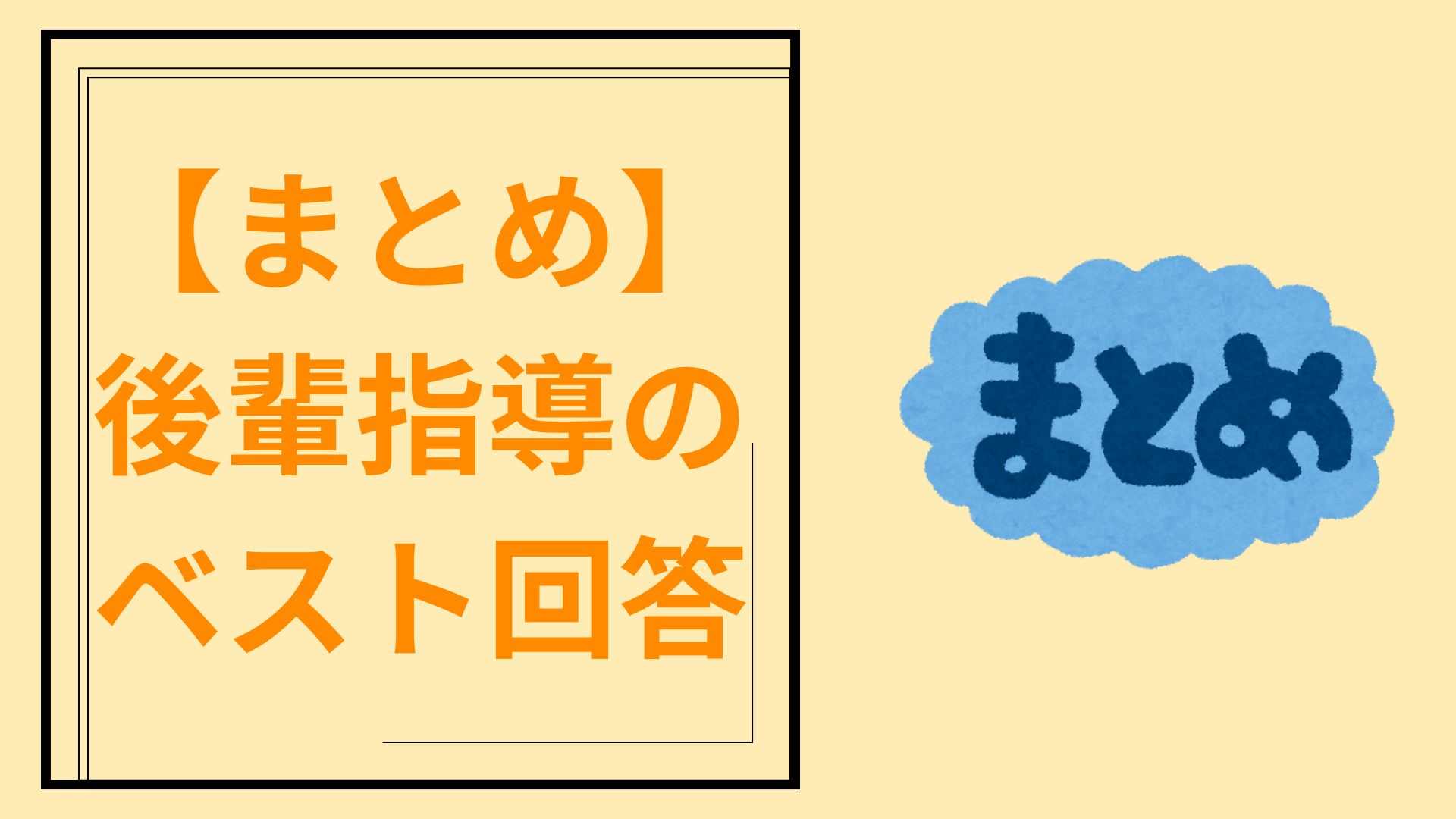
社会人経験者枠の公務員面接では、ただ「教える」だけの指導は高評価を得にくくなっています。
求められるのは、相手の考えを引き出し、一緒に考え、行動変容を促す指導です。
今回ご紹介した、
- 「やり方を教える・質問しやすい環境づくり」だけでは不十分な理由
- 「自分の頭で考えられる環境をつくる」指導の本質
- 「どこが難しいか、理由を一緒に考える」スタンス
上記を意識し、具体エピソードを添えれば、面接官から「現場で頼れる存在になってくれそうだ」と高く評価されるはずです。
ぜひこの考え方を面接対策に取り入れてみてください。
失敗の原因を事前に掴んでミスを回避しよう!
面接をコントロール出来れば試験は思いのまま!
自慢することが何もない人は今すぐ読んでください!