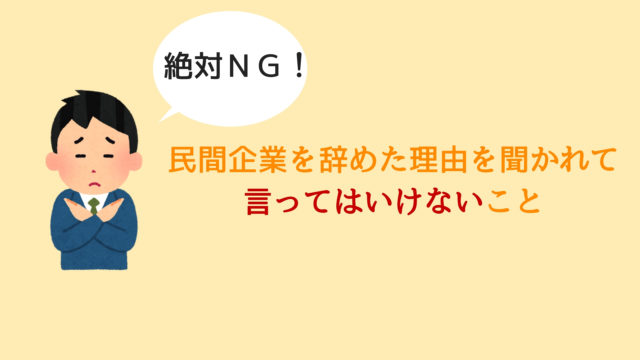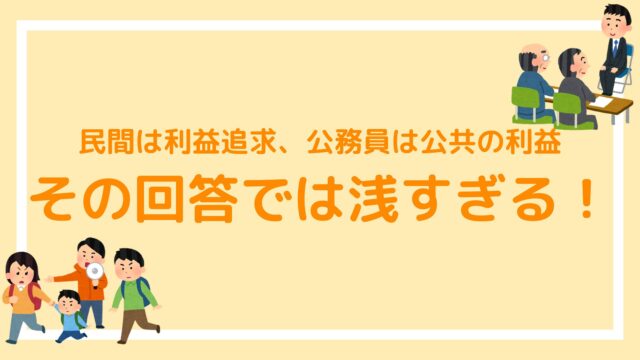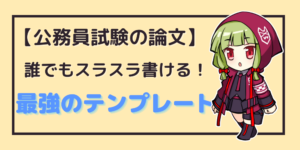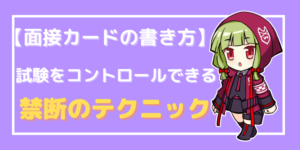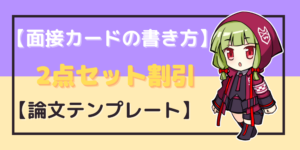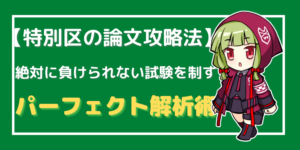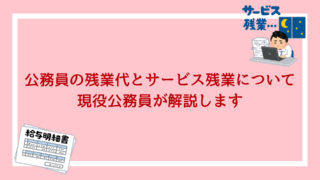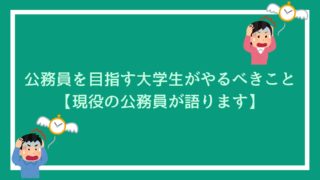公務員試験の面接では、必ずといっていいほど、
という質問が出てきます。
この質問、実は単なる治安や災害対策のことだけを指しているのではなく、その自治体の理念やあなたの価値観を見極める意図があります。
というわけで、
本文では、
- 面接官の心に響くベストな回答例
- その考え方の根拠
を詳しく解説します。
これを読めば、ただ「安全な街です」と答えるだけの受け答えから脱却し、深みのある答えができるようになります。
もくじ
「安心・安全なまち」とは、「社会的に弱い立場にある人たち平和に暮らせる状態」
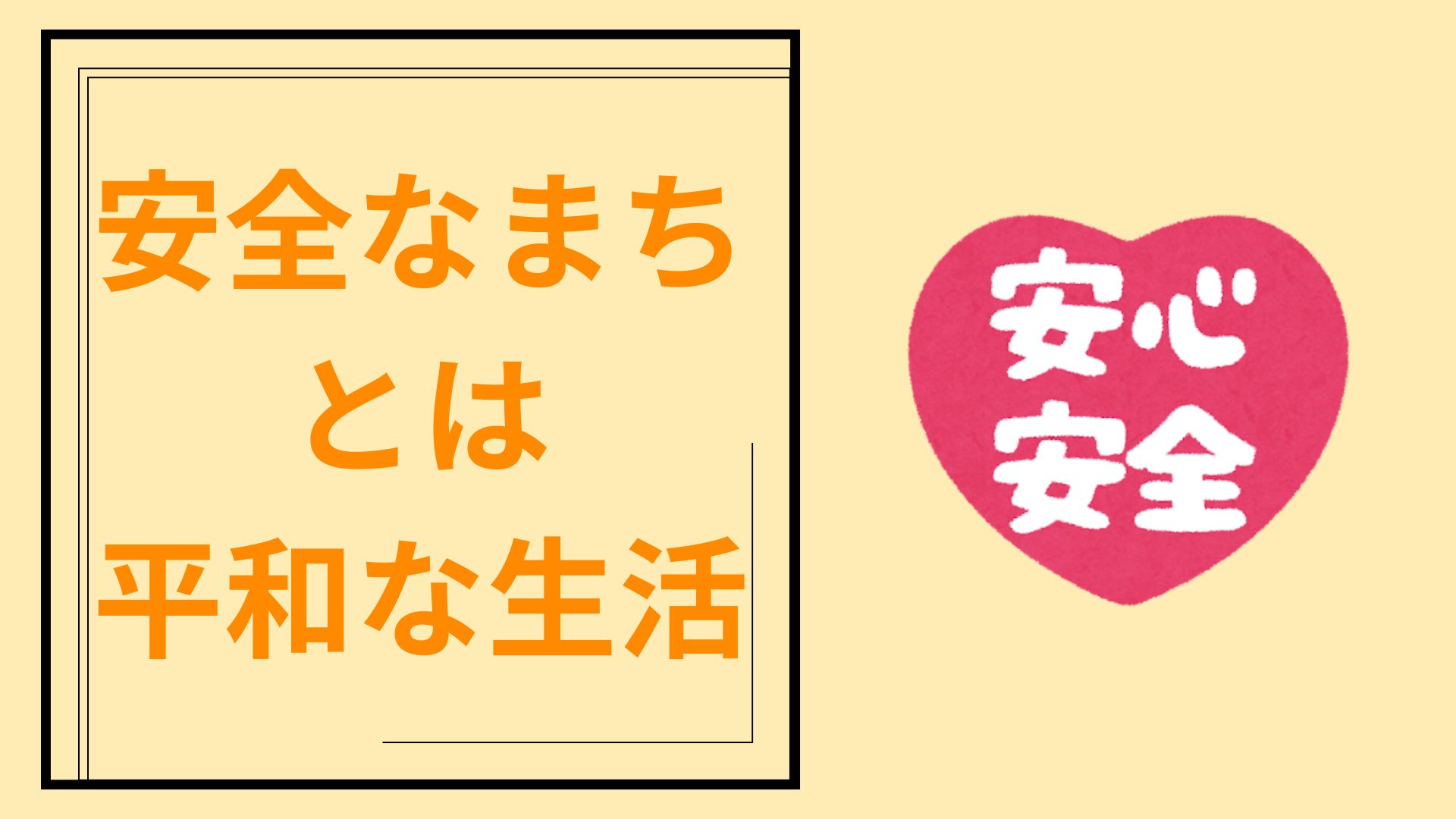
まず、答えの核心はここです。
多くの受験者は、
「治安が良い」
「災害が少ない」
「交通事故が少ない」
といった表面的な答えを返してしまいがちです。しかし、本質は違います。
本当に目指すべき「安心・安全なまち」とは、
「社会的に弱い立場にある人たちが、当たり前のように命を守られ、尊重される状態」
であるべきです。
なぜなら、社会の安全・安心の水準は「最も弱い立場の人がどれだけ守られているか」で決まるからです。
例えば、車椅子の方が自由に移動できる街は、高齢者や子ども連れも移動しやすい。
災害時に外国人に情報が行き届く街は、日本人にとっても安心です。
つまり、弱者視点の施策こそ、住民全体の安心・安全につながります。
体の不自由な人、外国人、高齢者、子どもの視点に立って考える
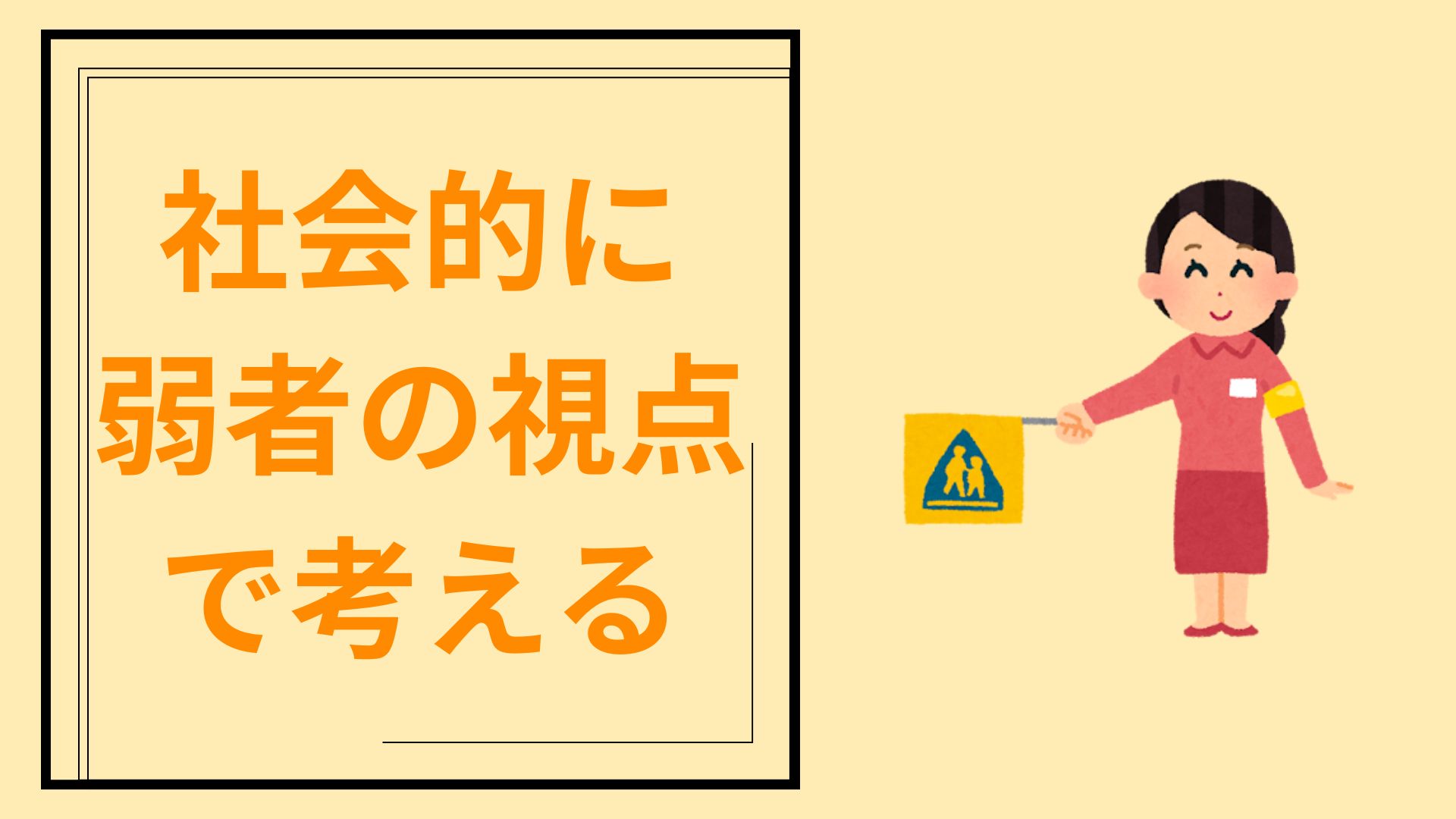
それでは具体的にどのような状態が理想なのか、4つの視点で解説します。
1. 体の不自由な人の安心・安全
段差のない歩道、音声信号、点字ブロックだけではありません。
避難所でのバリアフリー設備、災害時の移動支援体制も必須です。
さらに災害情報が音声や手話動画、文字など複数の手段で届くことも安心の条件です。
普段の生活から緊急時まで、一貫した支援体制が整った街こそ「安心・安全なまち」と言えます。
2. 外国人の安心・安全
多文化共生の観点から、外国人住民にとっても暮らしやすい街が求められます。
災害時の多言語情報の提供、病院や役所での通訳支援、地域イベントへの参加機会の保障。
日本語が十分でなくても安心して行政サービスを受けられ、困ったときに頼れる場があることで、その街は外国人にとっても安心・安全な場所となります。
3. 高齢者の安心・安全
超高齢社会の今、高齢者の安全は街づくりの最重要テーマです。
徘徊高齢者の見守りシステム、買い物支援、孤独死防止の地域ネットワーク。
さらに認知症高齢者がトラブルを起こした場合も、地域全体で受け止められる環境が安心を支えます。
4. 子どもの安心・安全
不審者対策、通学路の安全確保、学校の防災体制はもちろん、虐待の早期発見と対応、子どもの居場所づくりも重要です。
子どもが安心して育ち、自分の意見を言える環境があることが、その街の未来の安全につながります。
質問に対するベストな回答例
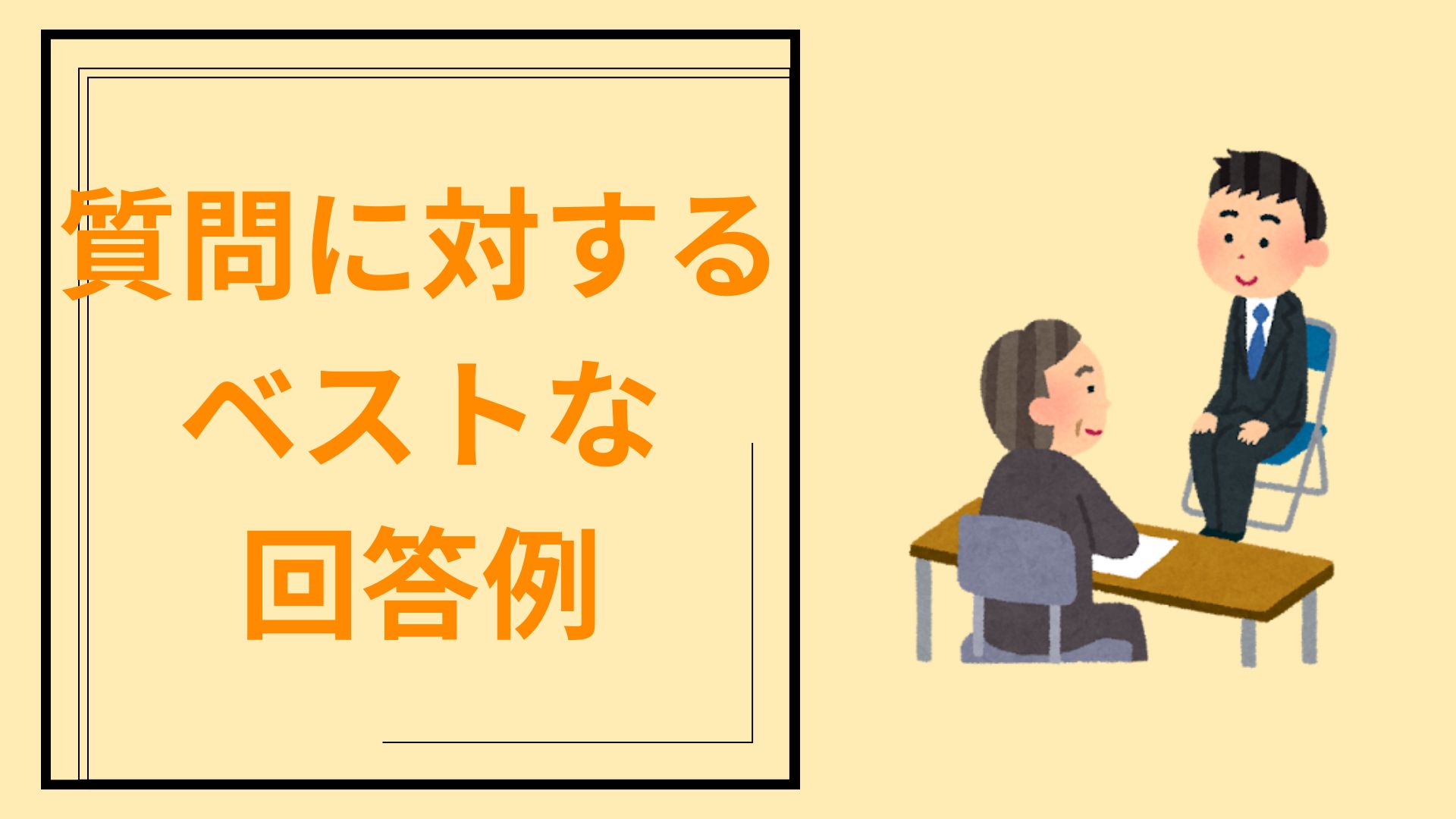
実際の面接では、以下のように答えると効果的です。
私が考える『安心・安全なまち』とは、災害や犯罪から命を守ることはもちろん、社会的に弱い立場にある方々が、暮らしの中で不安を感じずに生活できる状態だと思います。
例えば、災害時に外国人の方にも迅速に多言語で情報提供がなされ、高齢者の避難支援体制が整い、子どもや障がいのある方も安心して過ごせる環境が整っている街こそ、本当の意味での安心・安全なまちだと考えます。
そのために、普段から住民同士の交流や、多様な意見を取り入れた行政運営を大切にし、多様なリスクに備えた仕組みづくりを進めたいと考えています。
面接官が評価するポイント

面接官が評価するポイントは次のとおりです。
- 具体的に誰の立場に立って考えたか
- 安心・安全の定義を一段深めたか
- 具体策や施策への意欲を述べたか
- 社会全体の安心・安全と個別支援の両方を語れているか
この4点を押さえれば、他の受験者よりも頭ひとつ抜けた印象を残せます。
まとめ:「安心・安全なまち」とは
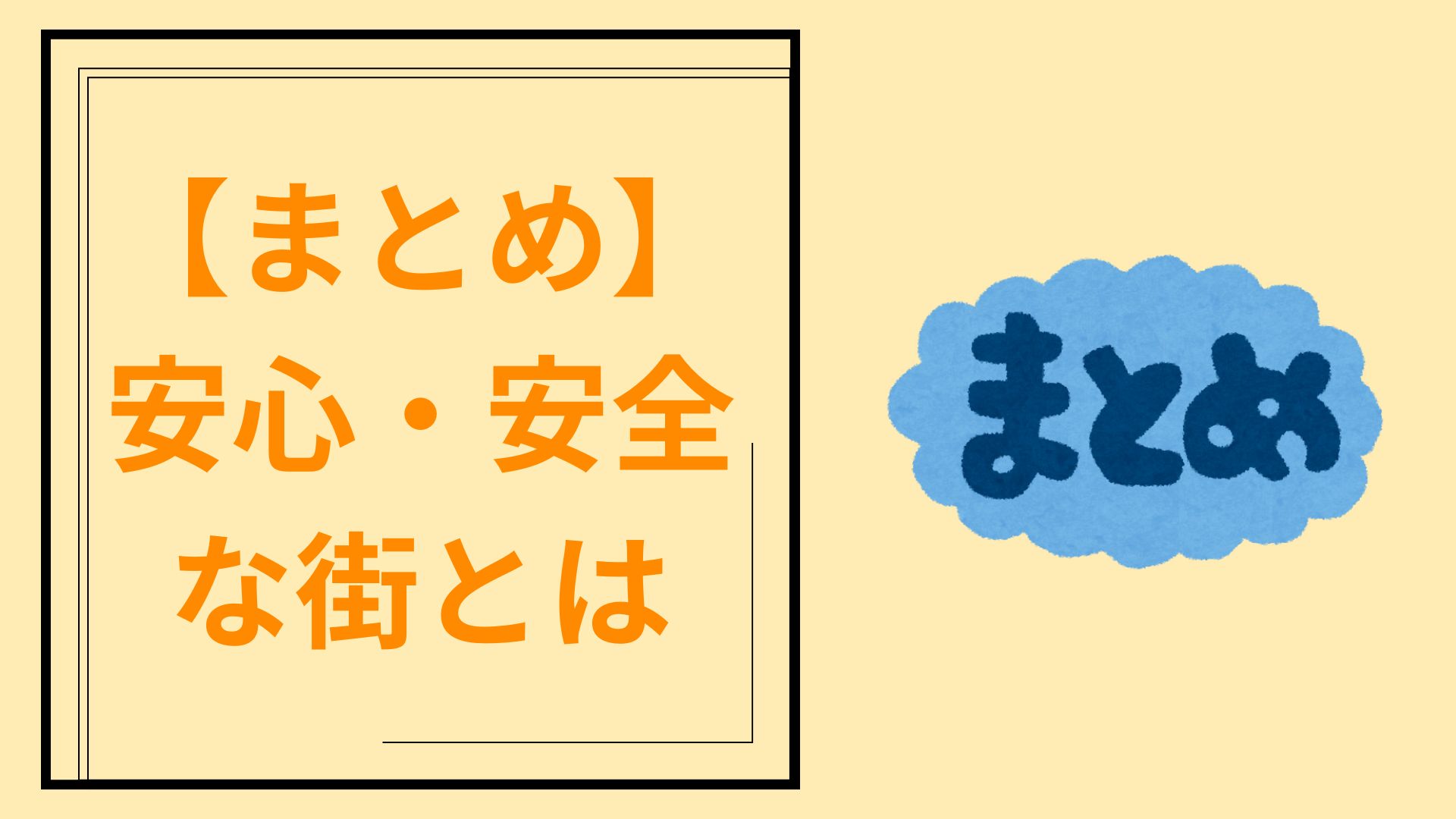
今回ご紹介した、
- 体の不自由な人
- 外国人
- 高齢者
- 子ども
上記4つの視点を取り入れた上で、自分自身の考えや志望する自治体の特性を踏まえて答えることができれば、きっと他の受験者と差をつけることができるでしょう。
面接官は住民目線を大切にしながら、自ら課題を発見し、その改善に前向きに取り組める人物を求めています。
決してテンプレート的な答えではなく、自分の経験や価値観と照らし合わせた言葉で答えれば、必ず面接官の印象に残るはずです。
さらに、安心・安全の概念は今後も時代とともに変わります。
昔は治安の良さや交通安全だけで評価されていたまちづくりも、今では防災・防犯だけでなく、福祉、防災教育、ICTを活用した見守り、孤独死防止、LGBTQ支援など、きめ細かな行政サービスが求められるようになりました。
だからこそ面接の場でも単純な答えではなく、
という主体的な意見を述べることが求められているのです。
今回の記事のまとめとして、改めて大切なポイントを整理します。
- 「安心・安全なまち」とは、単なる治安や防災の問題ではない
- 社会的に弱い立場の人々が命を守られ、安心して生活できる状態を目指すことが本質
- 体の不自由な方、外国人、高齢者、子どもという4つの視点を必ず取り入れる
- 弱者支援の充実は、結果として地域全体の安心・安全に繋がる
- 行政職員として、その視点を常に意識し、現場の課題解決に取り組む姿勢が求められる
この考え方を踏まえたうえで、自分の言葉で答えられるよう準備しておくと、面接の際に確かな自信を持って臨めるはずです。
面接の成否は、ほんの少しの発想の差と準備の質で決まります。
しっかりと対策を重ね、納得のいく面接に臨んでくださいね
失敗の原因を事前に掴んでミスを回避しよう!
面接をコントロール出来れば試験は思いのまま!
自慢することが何もない人は今すぐ読んでください!